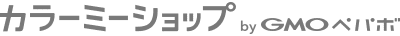半固定抵抗の使い方
半固定抵抗はドライバーで上面のつまみを回して抵抗値を変える部品です。

中には抵抗体が入っていて、ここにつまみに連動した回転する端子を当てて、抵抗値を分割できるようにしています。
このような構造から、1番ピンと2番ピン、3番ピンと2番ピンの間で、抵抗値は以下のようになります。
1番ピンと2番ピンの間 ・・・・ つまみを右に回すと抵抗値が大きくなる。
3番ピンと2番ピンの間 ・・・・ つまみを右に回すと抵抗値が低くなる。

つまみを右に回した時に抵抗値が大きくなるようにしたいときは、1番ピンと2番ピンだけを使えば良いことになりますが、このようなときは慣例的に2番ピンと3番ピンをショートさせて、<1番ピン>と<2番ピン+3番ピン>の間で使うことにします。
これは半固定抵抗の回転する端子(2番ピン)の故障で、抵抗体から浮いてしまったときに抵抗が何も無い状態(開放状態)になるのを防ぐ目的です。
(2番ピンと3番ピンがショートされていれば、2番ピンが浮いてしまっても1番ピンと3番ピンの間で抵抗値が保たれることになります)

当店のキットでも3本ある端子のうち2本をショートさせるように、説明書の組み立て例を書いています。















 クレジットカードでのお支払いがご利用できます。
クレジットカードでのお支払いがご利用できます。